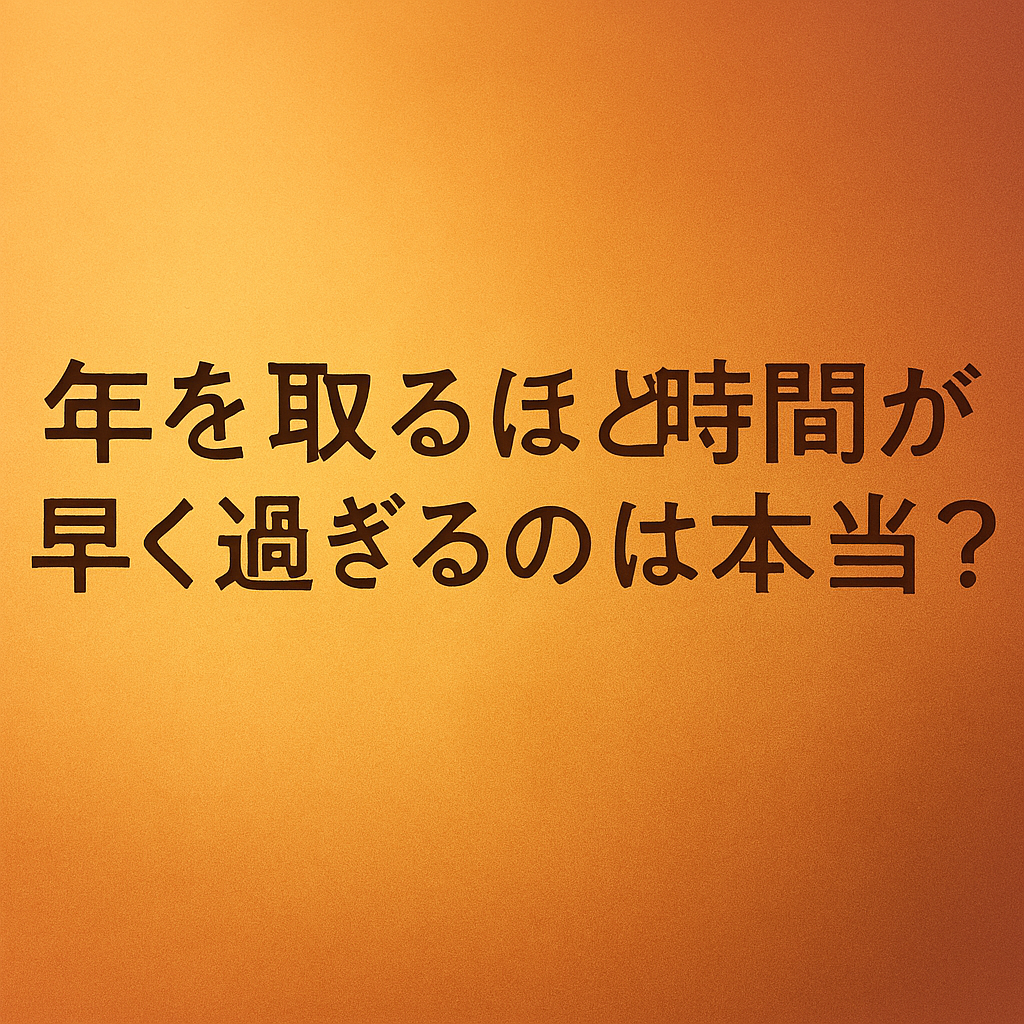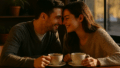「年を取るほど時間が早く過ぎる」と感じたことはありませんか?
子どもの頃は1年がとても長かったのに、大人になると気づけば「もう年末…?」。
この不思議な感覚には、心理学や脳科学に基づいた明確な理由があるんです。
この記事では、「年を取るほど時間が早く過ぎるのは本当なのか?」をテーマに、
心理学の「ジャネーの法則」や脳の働き、そして日常で時間をゆっくり感じるための実践法まで、
やさしく丁寧に解説します。
読めばきっと、「時間の感じ方」を変えるヒントが見つかるはず。
あっという間に過ぎていく毎日に、「もう少し長く生きた実感」を取り戻していきましょう。
年を取るほど時間が早く過ぎるのは本当?心理学で解説
年を取るほど時間が早く過ぎるのは本当なのか、心理学的に解説します。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
①「ジャネーの法則」とは
まず、このテーマを語る上で外せないのが「ジャネーの法則」です。これは19世紀のフランスの哲学者ポール・ジャネーが提唱した心理学的法則で、「人生のある期間がその人の年齢に反比例して短く感じられる」というものなんです。
たとえば、10歳の子どもにとって1年は人生の10分の1。でも、50歳の大人にとって1年は人生の50分の1。つまり、同じ1年でも、年齢が上がるほど“体感的な割合”が小さくなり、短く感じるという理屈です。
これを聞くと、「なるほど、確かに理屈としては納得できるな」と思いませんか? 子どもの頃は1年がとても長く感じたのに、大人になるとあっという間に過ぎてしまう。その違いは、この“相対的な時間の長さ”にあるんです。
ちなみにこの法則は、多くの心理学者がその後も検証しており、「時間感覚は主観的に変化する」という考え方の基礎にもなっています。つまり、単なる感覚ではなく、心理学的にも“年を取ると時間が早く感じる”のは本当だというわけです。
筆者も30代を過ぎてから、「あれ?もう年末?」と驚くことが増えました。まさにジャネーの法則を実感している瞬間ですよね。
②脳の情報処理量が減る理由
次に注目したいのが「脳の情報処理量の変化」です。若い頃は、脳が常に新しい刺激を受け取って、フル回転で情報を処理しています。ところが、年を重ねると同じような情報や刺激が増えてくるため、脳が“慣れてしまう”んです。
これは、脳が「新しい情報」を特に重視するという性質を持っているから。新しい環境、新しい出会い、新しい経験があるほど、脳はそれを細かく記録しようとするので、時間を“長く”感じやすいのです。
一方で、毎日が同じようなルーティンになると、脳の処理が効率化されて“もう知っている情報”としてスルーするようになります。その結果、記憶が薄くなり、体感的には「時間があっという間に過ぎた」と感じてしまうのです。
言い換えると、脳が“省エネモード”になっている状態ですね。これもまた、年齢とともに時間が早く感じる理由のひとつです。
筆者も同じ毎日を繰り返しているときほど、「え、もう週末?」と驚くことが多いです。まさに脳が刺激不足になってるサインかもしれません。
③体験の新鮮さが減るから
子どもの頃の1日は、まるで冒険のように感じましたよね。新しい遊び、初めての場所、知らない人との出会い——どれもが新鮮で、強く記憶に残ります。大人になると、そうした「初めての経験」が減ることで、時間が短く感じるようになります。
心理学的には、新鮮な体験が多いほど脳内の記憶が濃密になり、その結果「長く感じる」と言われています。逆に、ルーティンが続くと“あっという間”に過ぎたように感じるんですね。
たとえば、旅行に行った週と、いつもの仕事の週を比べてみるとわかりやすいです。旅行の週は写真や思い出がたくさん残りますが、仕事の週は「何をしてたっけ?」と思うこともあるでしょう。この「思い出の密度」の差こそが、時間の感じ方を変えているんです。
だからこそ、大人になっても「新しいことに挑戦する」のはとても大切。小さな変化でも、脳にとっては新鮮な刺激になります。いつもと違う道を歩く、初めての料理を作ってみる、そんなことでも十分なんですよ。
④感情の動きが少なくなるから
年を取るほど、感情の波が穏やかになります。もちろんそれは成熟の証でもあるのですが、一方で時間の感じ方に影響を与える要因でもあるんです。
感情が強く動くと、脳はその瞬間を「重要な出来事」として記憶します。だから、恋愛の始まりや試験の緊張感など、感情が大きく揺れたときほど、時間が濃く感じられるんです。
しかし、大人になると感情の起伏が減り、「まぁこんなものか」と受け流す場面が増えます。すると、1日の印象が薄くなり、結果的に時間が早く感じてしまうわけです。
つまり、“感情の振れ幅”が、時間の長さを左右しているんですね。感情の動きを意識して生活するだけでも、体感時間は変わるんですよ。
⑤年齢とともに記憶の密度が変わる
そしてもうひとつ大きな要因が、「記憶の密度の変化」です。年齢を重ねるにつれて、脳が記憶を“整理”する能力が上がり、似たような出来事はまとめて記録される傾向にあります。
子どもの頃は、似たような日でも細かく覚えているのに、大人になると「この前の週末、何してたっけ?」となることが増えますよね。これは、脳が情報を圧縮して処理しているからなんです。
結果として、記憶がスカスカに感じられ、「この数年、あっという間だったな」と思うようになるわけです。つまり、時間が早く感じるのは“記憶の圧縮”による錯覚とも言えます。
この仕組みを知っておくと、「どうすれば時間を濃く感じられるか」も見えてきますね。次の章では、科学的に見た時間感覚の仕組みをもう少し掘り下げていきます。
時間が早く感じる科学的な理由を徹底解説
時間が早く感じる科学的な理由について徹底的に解説します。
心理学的な説明に続いて、今度は科学的な視点から見ていきましょう。
①脳の時間感覚のメカニズム
まず、「そもそも時間を感じるのはどこ?」という疑問から。実は、時間の感覚は脳の「前頭前野」と「小脳」、「海馬」など、複数の領域が協力して作り出しているんです。
脳は、外界からの刺激を「順番通りに処理」することで“時間の流れ”を認識しています。つまり、私たちが「時間が流れている」と感じるのは、記憶と感覚の積み重ねによって作られた“錯覚”に近いんです。
このメカニズムは非常に繊細で、注意力や感情の状態によっても変化します。たとえば、退屈な会議の1時間は永遠に感じるのに、好きな映画の2時間は一瞬ですよね。これは、脳が「情報密度の高い時間」を長く、「単調な時間」を短く感じるためです。
つまり、時間の感じ方は“時計の針”ではなく、“脳の処理速度”で決まるんですよ。
②加齢によるドーパミン分泌の変化
もうひとつの大きな要因が、「ドーパミン」という神経伝達物質の変化です。ドーパミンは「やる気」「快感」「興奮」と深く関わる物質で、時間の感じ方にも強く影響しています。
若い頃は、新しいことに出会うたびにドーパミンが分泌され、脳が活発に反応します。だから、1日が長く、刺激的に感じるんです。ですが、年を取るとドーパミンの分泌が少なくなり、同じ出来事にも「新鮮さ」や「ワクワク感」を感じにくくなります。
その結果、脳が「時間を記録する密度」が下がり、あっという間に感じるようになるのです。
ドーパミンは、まさに“体感時間を引き延ばすホルモン”とも言えます。大人になっても新しい趣味を始めたり、感動する体験をすることは、このドーパミンを刺激して時間感覚を取り戻す大きな鍵なんですよ。
③日常のルーティン化と習慣脳
科学的にも「ルーティン化」は、時間を早く感じる最大の原因のひとつとされています。脳は基本的に“新しいこと”よりも“知っていること”を好む傾向があります。なぜなら、省エネで安全だからです。
しかし、毎日同じような仕事、同じ道、同じ人とだけ関わる生活をしていると、脳が「処理済み」と判断して記録を省略してしまいます。結果的に、「あれ?今週何してたっけ?」という現象が起きるんです。
この状態を専門的には「習慣脳」と呼びます。つまり、無意識で処理できることが増えると、時間を“省略して感じる”ようになるのです。
ちょっと怖いですよね。でも、逆に言えば、「意識的に変化を作る」ことで時間を取り戻すこともできるんです。
④時間の「記録」と「記憶」の違い
ここでおもしろいのが、脳科学的に見ると「時間の記録」と「時間の記憶」は別のプロセスで処理されているという点です。
たとえば、退屈な1日を過ごすとき、その場では「長いなぁ」と感じます。でも、後から振り返ると「もう終わってた」と感じます。逆に、充実した1日はあっという間に感じるけれど、後から振り返ると「濃かった」と記憶されています。
つまり、“今この瞬間の時間感覚”と“あとからの記憶上の時間”は別物なんです。
この違いを理解しておくと、「どう過ごせば人生を長く感じられるか」のヒントが見えてきます。短く感じる時間を「記憶に残る時間」に変えれば、結果的に“長く生きた実感”が得られるんですね。
⑤脳科学から見る「体感時間」
脳科学では、“体感時間”は実際の時計時間とはまったく異なるとされています。たとえば、緊張状態や集中状態ではアドレナリンが分泌され、脳が「より多くの情報を処理」します。そのため、時間がゆっくり進んでいるように感じるんです。
一方で、退屈なときや習慣化された作業中は、脳の処理が自動化され、情報がスルーされます。これにより「もうこんな時間?」という現象が起こるわけです。
つまり、時間の感じ方をコントロールするには、「脳がどれだけ情報を処理しているか」を変えればいい。集中する、感動する、挑戦する——これらはすべて時間を“引き延ばすスイッチ”なんです。
筆者も、旅先で1日を過ごすと「あれ、まだ1日しか経ってないの?」と感じることがあります。これは、脳が普段よりも多くの刺激を処理している証拠なんですよね。
つまり、時間を“濃く生きる”ことこそが、年齢に関係なく時間を長く感じる秘訣なんです。
子供のころと大人の時間の感じ方の違い5つ
子供のころと大人の時間の感じ方の違いについて詳しく解説します。
それでは、子供の頃の“ゆっくりした時間”と、大人になってからの“早すぎる時間”の違いを順に見ていきましょう。
①初体験が多い子供時代
子供の頃は、毎日が「初めて」の連続でしたよね。初めて自転車に乗れた日、初めて遠足に行った日、初めて友達の家に泊まった日。どの瞬間も、強く印象に残っているはずです。
心理学では、「新しい経験」が多いほど時間を長く感じると言われています。これは、脳が“未知の情報”を細かく処理しようとするため。新しい出来事を理解しようと、たくさんの神経が動くんですね。
子供の頃の1年がとても長く感じたのは、そうした「初めて体験の連続」だったから。言い換えると、脳が常にフル稼働していた時期なんです。
一方で大人になると、「もう経験済み」「見たことある」と判断することが増えます。その結果、脳が処理を省略し、体感時間が短くなっていくんです。
つまり、時間が長く感じるか短く感じるかは、“初体験の数”に大きく関係しているんですよ。
②大人になると新しい刺激が減る
大人になると、日々の生活がパターン化されていきます。朝起きて仕事に行き、帰ってご飯を食べて寝る。この繰り返しが続くことで、脳にとって新鮮な刺激が少なくなるんです。
脳は“変化”が少ないときに時間を早く感じます。なぜなら、同じ情報を繰り返し処理する必要がないから。結果として、「あっという間に1週間が過ぎた」「もう年末か」という感覚になるんですね。
逆に、旅行や転職、新しい趣味を始めたときなどは時間がゆっくりに感じます。これは、脳が新しい情報を処理するために“集中モード”になるからです。
つまり、日常が刺激に乏しいほど、時間は“圧縮”されて感じるんです。年を取るほど時間が早く過ぎるのは、科学的にも説明がつく現象なんですよ。
筆者も最近、同じカフェに通いすぎて時間の流れが速く感じるので、たまに違う席に座るようにしてます(笑)ちょっとした変化でも効果あるんですよ。
③感情の起伏の差
子供の頃は、毎日がドラマのように感じませんでしたか?嬉しい、悲しい、怒った、楽しい――感情の振れ幅がとても大きかったですよね。
心理学では、感情の起伏が大きいと時間が長く感じられるとされています。感情が動く瞬間、脳はその出来事を「重要な記憶」として強く刻むためです。
しかし大人になると、経験を積むことで感情をコントロールできるようになり、同時に“慣れ”が生まれます。そのため、同じ出来事でも心が大きく動かなくなり、時間が淡々と流れてしまうのです。
つまり、感情の動きが少ないほど、時間は早く感じます。大人になるというのは、“感情の起伏を失うこと”でもあるんですね。
だからこそ、意識的に感動する時間を作ることが大事なんです。映画を観て泣く、美しい景色を見て心を震わせる――そんな瞬間が、時間を「濃く」してくれます。
④時間を意識する頻度の違い
もう一つの大きな違いは、「時間をどれだけ意識しているか」です。子供の頃は、時間なんて気にせず遊びに夢中になっていましたよね。気づけば夕方、親に「もう帰りなさい!」と言われて初めて時間を意識するような感じでした。
一方で大人になると、「何時に出勤」「何時までに納期」「もうこんな時間…」と、常に時計とともに生活しています。時間を細かく意識することが、逆に“時間の早さ”を感じさせてしまうんです。
脳は「未来の予定」ばかり考えていると、今この瞬間を処理するリソースが減ります。つまり、意識が“今”ではなく“次”にある状態。これが、体感時間を短くしてしまう原因の一つなんです。
いわゆる「マインドフルネス(今に集中する)」は、この現象を逆転させるための方法なんですよ。
⑤過去との比較で早く感じる心理
そして最後は、「過去との比較」という心理的要因です。年を重ねるごとに、「去年もこんな感じだった」「あの頃と比べて今は早いな」と、過去を基準にして時間を感じるようになります。
つまり、記憶の中で“似たような1年”が増えるほど、脳は「もう見たことある情報」として処理し、体感的に短く感じるんです。
これを心理学では「比較時間錯覚」と呼びます。たとえば、同じ1年でも「環境が変わった年」と「同じ職場・同じ人・同じ生活の年」とでは、体感スピードがまったく違います。
変化が少ない年ほど、「あっという間に過ぎた」と感じるのはこのためなんですね。
つまり、時間の速さを止めるには、“過去と違う今”を意識的に作ることが大事なんです。小さな変化でも、心理的には大きな効果があります。
時間を長く感じるための方法7選
時間を長く感じるための方法を7つ紹介します。
年を取るほど時間が早く感じる――でも、それは「感じ方」であって、変えることができるんです。ここでは、科学的にも効果がある“時間をゆっくりに感じる方法”を紹介しますね。
①新しいことを始める
最も効果的な方法は、なんといっても「新しいことを始める」ことです。これは脳を刺激し、ドーパミンの分泌を促す“時間を引き延ばすスイッチ”のようなものなんですよ。
例えば、今までやったことのない趣味を始めるのもおすすめ。料理でも筋トレでも語学でも構いません。「新しいこと」をするとき、脳は未知の情報をたくさん処理しようとするので、時間が濃く感じられます。
心理学ではこれを「経験の新奇性効果」と呼びます。つまり、新しい体験をすると、脳がそれを詳細に記録するため、同じ時間でも“長く”感じるんです。
筆者も最近、陶芸教室に行ってみたんですが、たった2時間がすごく充実していて、「1日分くらいの濃さがあったな」と感じました。やっぱり新しい体験は、時間を“伸ばす”んですよね。
②日常に変化をつける
「新しいことを始めるほどの余裕はない」という人も大丈夫です。小さな変化でも効果はあります。たとえば、いつもと違うルートで通勤する、違うカフェに寄る、髪型を変えるなど。
脳は、予想外の刺激を受け取ると「おっ」と反応します。その瞬間、脳の注意力が高まり、情報処理の密度が上がるんです。その結果、時間が長く感じられます。
つまり、“非日常”を作るのではなく、“日常の中に非日常を紛れ込ませる”ことがポイントなんです。
いつも通る道で、空を見上げてみるだけでも気づきが変わります。忙しい日々の中でも、こうした小さな変化を意識してみてくださいね。
③感情を動かす体験を増やす
感情を動かす瞬間ほど、時間を濃く感じるものはありません。感動する映画、泣ける本、笑える友人との会話、ドキドキする出来事――こうした“心が動く瞬間”が多いほど、1日が豊かで長く感じられます。
脳科学的にも、感情が強く動いた出来事は、扁桃体という領域を通じて強く記憶に残ります。だから、感情を伴う時間は、後から振り返っても「長かった」と感じるんです。
一方で、何も感じない日々が続くと、脳は「この日は記録しなくていい」と判断してしまいます。まるで早送りのように時間が流れてしまうんですね。
感情の動きは、人生の濃度そのもの。だから、「心が動く選択」を意識的にしていくと、時間の流れがゆっくりに戻っていきます。
④「初めて」を意識的に作る
「初めて」は、子供時代に時間を長く感じさせていた最大の要因でした。その“初めて”を大人になっても意識的に作ることができれば、時間の濃さを取り戻せます。
たとえば、「初めての場所に行く」「初めての料理を食べる」「初めての人に会う」。どんなに小さなことでもOKです。大事なのは、“初めてだ”と意識して体験すること。
意識するだけで、脳が「これは新しい情報だ」と反応し、記憶の密度が上がります。
筆者も、「いつものスーパー」ではなく、あえて別の地域のスーパーに行ってみたことがあるのですが、それだけでまるで小旅行のような気分になれました。初めての刺激って、ほんとに時間を豊かにしてくれるんですよね。
⑤マインドフルネスで「今」に集中する
「時間が早い」と感じる大きな理由のひとつが、“今を生きていない”ことです。人はつい、過去を悔やんだり、未来を心配したりして、今この瞬間を意識できていないんです。
マインドフルネス(Mindfulness)は、その“今”に意識を戻すトレーニング法。呼吸、音、感覚、姿勢――そうしたものに注意を向けることで、時間がゆっくりと流れる感覚を取り戻せます。
たとえば、朝のコーヒーを飲むときに「香り」「温かさ」「口当たり」に集中する。それだけでも、数分間が豊かな体験に変わります。
時間を伸ばすとは、「時間を感じ取る力を取り戻すこと」なんですよ。
⑥スマホ時間を減らす
意外かもしれませんが、スマホは“時間を奪う最大の敵”なんです。SNSや動画を見ていると、気づいたら2時間経っている――そんな経験、ありますよね。
脳は、スマホの情報を“断片的”にしか処理していません。つまり、「あれ?何を見てたっけ?」という状態になりやすく、記憶に残らないんです。記憶に残らない時間は、“存在しなかった時間”として処理されます。
だから、スマホをダラダラ使うほど、「時間が早く感じる」ようになるんです。
1日の中で「スマホを触らない時間」を作るだけでも、驚くほど時間がゆっくりになります。たとえば夜寝る前の30分だけでも、本を読んだり、音楽を聴いたりして“脳をゆっくりモード”に戻してあげてくださいね。
⑦時間を記録する習慣をつける
最後におすすめしたいのが、「時間を記録する」こと。日記でも、写真でも、SNSでも構いません。自分の1日を“可視化する”ことで、記憶が濃くなり、時間がゆっくりに感じられるんです。
これは心理学でも「記録効果」として知られていて、体験を言語化・可視化することで、脳がその出来事をより深く認識します。
また、後から見返すことで「この1週間、けっこう色んなことしてたな」と実感でき、時間に対する満足度も上がります。
筆者も毎日、寝る前にスマホのメモに「今日よかったことを3つ」書くようにしています。これを続けていると、ほんの数週間で「時間が濃くなった感覚」が戻ってきますよ。
時間を記録するという行為は、まさに“今を生きること”そのもの。忙しい毎日こそ、意識して取り入れてみてくださいね。
時間の感じ方を変えると人生が豊かになる理由5つ
時間の感じ方を変えると人生が豊かになる理由について解説します。
「時間の感じ方を変える」というのは、単に“時間を遅くする”ことではありません。
それは、自分の人生を“丁寧に生きる力”を取り戻すことでもあるんです。
①人生を丁寧に味わえる
時間をゆっくり感じるようになると、人生の1つ1つの瞬間を丁寧に味わえるようになります。
たとえば、朝の光、コーヒーの香り、通りすがりの風――普段は通り過ぎていた“当たり前”の瞬間に幸せを見つけられるようになるんです。
時間を意識せず過ごしていると、1日は「やることリスト」で終わってしまいます。
でも、時間を感じながら過ごすと、「今この瞬間を生きている」という実感が増えます。
実際、幸福学でも「丁寧に生きる人ほど幸福度が高い」という研究結果があります。
小さなことを“味わう感覚”が、人生の豊かさを作るんです。
時間を丁寧に扱うことは、自分を丁寧に扱うこと。
日々を「こなす」ではなく、「味わう」。この意識の違いが、人生を大きく変えていきます。
②小さな幸せに気づける
時間の感じ方を変えると、日常の中に隠れていた“小さな幸せ”に気づけるようになります。
たとえば、好きな人と過ごす時間、夕焼けの色、季節の香り。
それらはすべて、“気づく心”があるからこそ感じられるんです。
忙しく過ごしていると、こうした小さな幸せを見逃してしまいがち。
でも、時間をゆっくり感じるようになると、「あ、こんなに心地よかったんだ」と思える瞬間が増えます。
つまり、“幸せの総量”は出来事の数ではなく、感じ取る力の深さで決まるんです。
筆者も、以前は1日の終わりに「今日もあっという間だったなぁ」としか思っていませんでした。
でも、今は「今日のコーヒー美味しかった」「夕方の風が気持ちよかった」と書き出すようにして、毎日が少しずつ豊かになっていきました。
③過去ではなく今を生きられる
時間を早く感じる人の多くは、「過去」や「未来」に意識が向きすぎています。
「あのときこうすればよかった」「次は何をしよう」――この繰り返しの中で、“今”が置き去りになっているんですね。
時間の感じ方を変えるとは、言い換えると「今ここ」を生きること。
過去も未来も、実際には存在していません。
存在しているのは、“今この瞬間”だけなんです。
マインドフルネスや瞑想を習慣にしている人が穏やかで幸福に見えるのは、
まさにこの“今を生きる”力を磨いているからなんです。
「今」を感じる力を取り戻すと、時間がゆっくりになり、人生の軸がブレなくなります。
④充実感が増す
時間を長く感じる生き方をすると、日々の充実感が圧倒的に増します。
なぜなら、「体験の密度」が濃くなるからです。
何気ない1日でも、新しい発見をしたり、心が動いたり、誰かと深く話したりすると、
「今日はいい1日だったな」と感じますよね。
この“満足感”は、時間の濃さと直結しています。
同じ24時間でも、「流れた時間」ではなく「刻まれた時間」にする。
その違いが、人生の質を大きく変えていくんです。
筆者も、以前は「1日が短い=悪いこと」だと思っていました。
でも今は、「短くても濃い1日ならいい」と思えるようになりました。
時間の“長さ”よりも“深さ”が大事なんですよね。
⑤「長く感じる毎日」が人生の満足度を上げる
最終的に言えるのは、時間を長く感じるほど人生の満足度は上がるということです。
人間の幸福度は、“どれだけ長く生きたか”ではなく、“どれだけ濃く生きたか”で決まります。
子供の頃の1日は「永遠のよう」に感じたのに、大人になると「もう1週間?」となる。
この違いを取り戻すには、“感じ方”を取り戻すことです。
新しい体験をする、感情を動かす、今に集中する――そうした積み重ねが、“濃い時間”を作ります。
そして、それを意識的に続けると、1日1日が「生きている実感」に変わります。
この感覚こそが、人生を豊かにしていく本当の意味での“時間の贅沢”なんです。
時間の流れを止めることはできません。
でも、“感じる時間”は、いつだって自分で変えられるんですよ。
まとめ|年を取るほど時間が早く過ぎるのは本当?
| 年を取るほど時間が早く過ぎる理由(心理学で解説) |
|———————————-|
| ①「ジャネーの法則」とは |
| ②脳の情報処理量が減る理由 |
| ③体験の新鮮さが減るから |
| ④感情の動きが少なくなるから |
| ⑤年齢とともに記憶の密度が変わる |
「年を取るほど時間が早く過ぎる」というのは、単なる気のせいではありません。
心理学的にも、脳科学的にも、年齢とともに時間の感じ方が変化するのは確かなんです。
その背景には、「ジャネーの法則」や「脳の情報処理の効率化」、そして「感情や刺激の減少」などが関係しています。
しかし、希望もあります。
時間の流れをコントロールすることはできなくても、「感じ方」を変えることはできるんです。
新しいことを始める、感情を動かす、今に集中する――そうした小さな積み重ねが、
1日を、そして人生そのものを“長く感じる時間”へと変えてくれます。
今この瞬間を丁寧に味わうことが、時間をゆっくりにする最も確かな方法です。
忙しさの中にある“今”を大切にして、毎日をもっと豊かに過ごしていきましょう。
参考:Why Time Seems to Speed Up with Age(Scientific American)
参考:Neuroscience of Time Perception(National Library of Medicine)