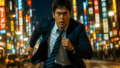4児の母であり、女優としても活躍する平愛梨さん。彼女が子どもたちに「1人1台のタブレット」を持たせているというニュースが話題になっています。
「まだ小さいのに早すぎるのでは?」と思う人もいれば、「デジタル教育の最先端!」と感じる人もいるでしょう。
実は、この決断の裏には、平愛梨さんならではの深い教育への思いと、時代を見据えた子育て哲学がありました。
この記事では、平愛梨さんの“タブレット教育”に込められた真意や、実際の家庭での取り入れ方、そしてメリット・デメリットまでを徹底解説します。
あなたの家庭でもすぐに活かせるヒントがきっと見つかるはずです。ぜひ最後まで読んで、子どもとの新しい学びの形を見つけてくださいね。
4児の母・平愛梨、子どもに1人1台タブレットを導入した理由
4児の母・平愛梨、子どもに1人1台タブレットを導入した理由について解説します。
それでは、順に見ていきましょう。
①平愛梨が語る教育への思い
平愛梨さんは、4児の母として忙しい毎日を送りながらも、子どもの教育に対して非常に前向きな姿勢を見せています。彼女が大切にしているのは、「自分で考えて、自分で選ぶ力」を育てることなんです。
芸能活動と家庭を両立する中で、彼女は「親が教えることよりも、子ども自身が興味を持って学ぶことの方が何倍も力になる」と話しています。だからこそ、タブレットという“個人の学びツール”を子どもに与える決断をしたそうです。
子どもが自分のペースで学び、好きな分野を伸ばせる環境を整える。それが彼女にとっての「今の時代の教育」なんですね。親が一方的に教えるのではなく、「学びのきっかけを与える」立場になるという考え方です。
この考え方には、教育評論家や発達心理学者からも賛同の声が多く寄せられています。まさに、デジタル時代の新しい母親像を体現しているといえますね。
私自身もこの考えにとても共感します。「親が全部教える」時代から「親が子どもの好奇心を支える」時代に変わってきているんですよね。
②なぜ「1人1台」なのか?その背景
平愛梨さんが「1人1台タブレット」を導入したのには、明確な理由があります。それは「子どもたち一人ひとりに違う個性と興味があるから」です。
4人の子どもたちが同じ教材、同じスピードで学ぶのは現実的ではありません。好きなことも、得意なことも違う。だからこそ、それぞれに専用のタブレットを持たせ、興味やレベルに合わせたコンテンツを選ばせているのだとか。
さらに、家族で海外を行き来することが多い平家では、デジタル機器を使うことで“どこでも学べる環境”を作ることができる点も大きな理由。Wi-Fiさえあれば、場所に縛られずに学びを継続できるんですよね。
また、教育現場でも「GIGAスクール構想」で1人1台タブレットが推進されています。その流れを自然に家庭教育にも取り入れている点で、彼女は時代の最先端を行っているといえるでしょう。
「子どもは未来の世界で生きる」——そんな視点から考えたら、デジタル教育は避けて通れない。平愛梨さんの決断には、そんな深い意図があるように感じます。
③家庭でのルールと使い方
平愛梨さんの家庭では、タブレットをただ自由に使わせるわけではありません。しっかりとした“ルール”を設けています。たとえば、学習時間と遊び時間の切り替え、スクリーンタイムの制限、そしてリビングでのみ使用すること。
このように、デジタル機器を「管理」するのではなく、「一緒に使う」という意識を持っているのが特徴です。親が監視者ではなく、共に学ぶパートナーという立ち位置なんですね。
実際に、平さんは「私も子どもと一緒に調べる時間が楽しい」と話しており、タブレットを通じて親子の会話や発見が増えたそうです。これがまさに理想的な“共育”スタイルです。
また、デジタル機器の使い方を教えることは、現代社会に必要なスキルを育てることにもつながります。ネットリテラシー、情報の取捨選択、マナーなど、小さいうちから身につけられるのは大きなメリットですよね。
ポイントは、「使わせる」ではなく「一緒に活用する」。これが平愛梨流の教育法といえるでしょう。
④長友佑都との教育観の違い
夫である長友佑都さんとは、教育に関してよく話し合うそうです。彼は「体を動かすこと」や「実体験」を重視するタイプ。一方の平愛梨さんは「知的好奇心」を大切にしています。
お互いの意見が違うときもありますが、そこに衝突はなく、むしろバランスが取れているようです。子どもには「デジタルで学ぶ力」と「身体で感じる力」の両方が必要だと考えているのだとか。
つまり、夫婦でそれぞれの強みを活かしながら、子どもたちに多面的な学びの環境を提供しているんですね。これは本当に理想的なチーム育児です。
「夫婦で教育観が違っても、それぞれの得意を活かせばいい」——平さんのこの言葉には、たくさんのママたちが共感したのではないでしょうか。
教育に“正解”はないけれど、“軸”はある。その軸が「子どもを信じること」なんです。
⑤タブレット導入で変わった子どもの様子
タブレットを導入してから、子どもたちにはさまざまな変化があったそうです。まず、学びへの主体性が高まったこと。自分から調べたり、動画を通して新しいことを学んだりする姿が増えたといいます。
また、兄弟それぞれの興味がより明確になった点もポイントです。長男はスポーツ動画、次男は恐竜図鑑、三男は英語学習アプリ、末っ子はお絵かきアプリ。それぞれが違う方向に興味を持つことで、自然と個性が伸びていったそうです。
さらに、平さん自身も「子どもの世界を知る」機会が増えたと話しています。親が知らないことを、子どもが教えてくれるようになったとも。
テクノロジーを通じて、親と子の立場がフラットになり、互いに学び合う関係になっていく。これがまさに、平愛梨さんが目指す“共育”の形なんですよね。
「タブレットで遊んでいるだけ」と思っていたら、実は学んでいた——そんな驚きを何度も経験しているそうですよ。
平愛梨流・タブレット教育のメリット5つ
平愛梨流・タブレット教育のメリット5つについて解説します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①自立した学びを促す環境づくり
平愛梨さんの教育の最大の特徴は、「自立した学び」を重視しているところです。タブレットを使うことで、子どもたちは自分の興味に合わせて学ぶことができます。たとえば、好きな動物の動画を見たり、英語の発音を真似したり、図形パズルで集中力を鍛えたりと、学びの形が自由なんです。
この「自分で選んで学ぶ」というプロセスが、まさに主体的な学びを育てます。従来のように「やらされる勉強」ではなく、「やりたい学び」に変わる瞬間なんですよね。これは子どもの自信や意欲にも直結します。
さらに、タブレットはすぐに結果が見えるという特徴もあります。正解・不正解がその場でわかることで、達成感が生まれ、モチベーションを維持しやすくなるんです。
平さんの家庭では、子どもが学習アプリで遊んでいる姿を見て「自然に学びが続いている」と感じることが多いそう。無理に机に向かわせなくても、子どもが自分から学ぶ習慣を身につけられるのは大きなメリットですよね。
「自分で調べる力」を育てる。それがデジタル学習の最大の価値なんです。
②デジタルリテラシーを早く身につけられる
今の時代、子どもたちは生まれたときからデジタルの世界に生きています。つまり、デジタル機器を正しく使いこなすスキル(=デジタルリテラシー)は、将来において「読み書き」と同じくらい大切な基礎能力なんです。
平愛梨さんは、タブレットを通じて子どもたちにそのリテラシーを早くから身につけさせています。たとえば、情報を検索する力、データを整理する力、ネット上でのマナーなど、学校だけでは学べないことが日常的に身につくのです。
特に印象的なのは、「使い方を教えすぎない」という姿勢。子どもが自分で試行錯誤しながら、自然とスワイプやタップを覚えていく様子を見守るそうです。これも「考える力」を育てるための一環なんですよね。
実際に、OECD(経済協力開発機構)の教育研究でも、デジタル機器を早期から正しく扱う子どもは、問題解決能力が高い傾向があると報告されています。平さんの教育方針は、まさにこの考え方と一致しています。
デジタルを“禁止する”のではなく、“正しく使う力を育てる”。それがこれからの時代に求められる教育なんですよね。
③親の時間にもゆとりが生まれる
4人の子どもを育てる平愛梨さんにとって、「時間」は何より貴重なもの。タブレット教育を導入することで、子どもが自分で学ぶ時間が増え、親の手が少し離れる瞬間が生まれます。
もちろん、“放置”とは違います。親がそばで見守りつつ、子どもが自分で進められる環境を整えることで、自然と時間に余裕ができるのです。その時間で、他の子どもの世話をしたり、家事をこなしたり、自分のリフレッシュ時間を確保できるようになったそうです。
また、親がリラックスしていると、家庭全体の空気も穏やかになります。心理学的にも、親のストレス軽減は子どもの安定に直結するという研究結果があります。
つまり、タブレット教育は“親のための教育サポート”という側面もあるんです。教育と育児の両立を助けてくれる現代のツールといえるでしょう。
「タブレットがあると、ちょっと一息つける」——これは多くのママたちに共感されるメリットですよね。
④海外生活との相性が良い
平愛梨さんと長友佑都さん一家は、長年イタリアなど海外で暮らしています。だからこそ、タブレット教育は“生活の一部”として欠かせないものになっているようです。
海外では日本語の教育環境が限られることもあり、タブレットを使えば「日本の教材」をどこでも使うことができます。逆に、英語や現地の言語を学ぶアプリも取り入れやすく、まさに“多言語教育”を実現できるんです。
さらに、海外ではデジタル学習が日本より進んでいる国も多く、子どもが自然にデジタル教育に馴染むことができます。友達とのコミュニケーションやオンライン授業でも、そのスキルが活かされるんですよね。
「どこにいても学べる」というのは、これからのグローバル時代にとても大切な考え方です。平愛梨さんが“1人1台タブレット”にこだわる理由のひとつが、ここにもあります。
家族で移動の多い生活をしているからこそ、学びを「持ち運べる」環境が必要なんですね。
⑤興味や才能を広げるきっかけになる
タブレットは、単なる学習ツールではありません。子どもたちの「好き」や「得意」を見つけるための“扉”でもあります。平愛梨さんの家庭では、子どもが自由にアプリを選べる時間を設けており、そこから思わぬ才能が開花することもあるそうです。
たとえば、音楽アプリで作曲に興味を持ったり、デザインアプリで絵を描くのが好きになったり。そうした“発見”が、後の習い事や夢につながっていくこともあります。
子どもの「やってみたい」を尊重する姿勢こそ、平さんが大切にしている教育観のひとつ。タブレットはそれを叶えるための“きっかけツール”なんです。
また、AIを活用した教育アプリなども登場しており、子どものレベルに合わせて最適な学びを提供してくれるのも魅力。まさに、個性に寄り添う教育が実現できる時代になりました。
「タブレットは、子どもの可能性を広げるための魔法の箱」——平愛梨さんの言葉が、そのすべてを物語っていますね。
タブレット教育のデメリットや心配点
タブレット教育のデメリットや心配点について解説します。
どんなに便利なツールでも、注意すべきポイントがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
①視力や健康面への影響
まず、最も多くの親が心配するのが「目への悪影響」です。長時間の画面使用は、どうしても視力低下や姿勢の悪化につながりやすいもの。特に成長期の子どもは、まだ筋肉や骨格が発達途中のため、姿勢が崩れやすいんですよね。
日本眼科学会でも、デジタル機器の使いすぎによる「VDT症候群(いわゆるスマホ老眼)」への注意が呼びかけられています。目の疲れ、頭痛、集中力の低下など、軽視できない影響も。
平愛梨さんの家庭でも、この点はしっかり意識しているようで、「1回の使用は30分まで」「寝る前1時間は使わない」などのルールを徹底しているそうです。
また、タブレットスタンドを使用したり、照明を工夫したりするだけでも目への負担は減らせます。つまり、ツール自体が悪いのではなく、「使い方次第」で健康的に活用できるということですね。
デジタル教育を取り入れるなら、健康面のケアも同時に行う——それが大切です。
②ネット依存・ゲーム依存のリスク
次に心配なのが、ネットやゲームへの依存です。タブレットには学習アプリ以外にも魅力的なコンテンツが多く、子どもがつい夢中になってしまうこともあります。
「気づいたら1時間以上YouTubeを見ていた」なんてこと、どの家庭でも起こりがちですよね。特に幼少期は“自制心”がまだ発達していないため、親のサポートが不可欠です。
平愛梨さんの家庭では、「学びの時間」「自由時間」「おやすみタイム」をしっかり区切ることで、依存を防いでいるそうです。また、タブレットの“ファミリー管理機能”を使って、利用時間を自動制限するのも効果的です。
ここで重要なのは、「禁止」ではなく「コントロール」。完全に取り上げると、逆に執着が強くなる場合があります。子どもと一緒にルールを作り、「自分で守る意識」を育てるのがポイントです。
親子で話し合いながら「どんな動画ならOKか」を決めていくことで、子ども自身もデジタルとの距離感を学んでいくんですよね。
③リアルな体験が減る懸念
タブレット学習を進めると、「現実世界での体験が減るのでは?」という不安の声もあります。確かに、画面上で完結する学びばかりになると、手を動かしたり、体を使ったりする機会は減ってしまいます。
しかし、平愛梨さんはそこもきちんとバランスを取っています。「デジタルは知識を広げるための手段。リアルな体験こそが心を育てる」と語っているんです。
例えば、タブレットで見た動物を、実際に動物園で観察してみる。料理アプリで覚えたレシピを一緒に作ってみる。そうした“実体験への橋渡し”としてタブレットを使っているのが特徴です。
要するに、「画面の中で終わらせないこと」が大切なんですよね。知識を“現実で使う”ことで、学びが深まります。
デジタルとリアルを行き来することで、子どもの感性はむしろ豊かになる。これはまさに、平愛梨流・バランス教育の真骨頂といえます。
④兄弟間の使い方トラブル
4人の子どもがいると、どうしても起こりやすいのが「順番トラブル」や「取り合い問題」。でも、ここで1人1台のタブレットを用意していることに意味があります。
「誰がどのアプリを使うか」「どの時間に使うか」でケンカになるのを防ぐため、それぞれの専用タブレットを持たせているんです。自分のものを大切にする感覚も育ちますし、責任感も芽生えます。
ただし、兄弟間の差が出ることもあります。「お兄ちゃんは勉強してるのに、弟はゲームしてる」といったケースですね。こうしたときは、親が一言「それぞれの使い方があっていいんだよ」と伝えるだけでも、家庭の空気が和らぎます。
平愛梨さんの家庭でも、「比較しない」「奪わない」「助け合う」を家族のルールとしているそうです。このスタンスがあるからこそ、4人の子どもたちがのびのびと育っているんですよね。
兄弟が多い家庭ほど、こうした「トラブルを防ぐ工夫」は参考になります。
⑤親が管理する負担の大きさ
タブレット教育は、親のサポートがあってこそ成り立ちます。学習アプリの選定、利用時間の管理、トラブル対応……正直、最初はかなり大変です。
特に、複数の子どもがいる場合は「誰が何を使っているか」を把握するだけでもひと苦労。でも、平さんはこの負担を「楽しみ」に変えています。子どもと一緒にアプリを選び、学びの進み具合を共有する時間を“親子のコミュニケーションタイム”としているんです。
また、最近では「家庭学習を見守るAIアプリ」や「ペアレンタルコントロール機能付きの端末」も増えてきました。こうしたツールを上手に使えば、親の負担も軽くなります。
つまり、「親が完璧に管理しよう」としないことがコツ。むしろ、子どもと一緒に考えながら使い方を決めていく方が、結果的にうまくいくんです。
親の役割は“監視者”ではなく“伴走者”。その意識があるだけで、デジタル教育はぐっと健全で、楽しいものになりますよ。
一般家庭でも真似できる?平愛梨流デジタル教育の取り入れ方
一般家庭でも真似できる?平愛梨流デジタル教育の取り入れ方について解説します。
平愛梨さんのような“タブレット教育”は、実は特別なものではありません。工夫次第で、どの家庭でも取り入れられる方法なんです。
①導入前に決めておく家庭ルール
タブレットを家庭に導入するときに最も大切なのは、「最初にルールを決めること」です。これを曖昧にすると、使いすぎや兄弟げんかなどのトラブルが起こりやすくなります。
平愛梨さんの家庭では、使う時間帯・使用目的・保管場所を明確にしているのが特徴です。たとえば「夜9時以降は使わない」「リビングでだけ使用」「学習が終わったらアプリで遊んでOK」といったルールですね。
ここでポイントなのは、ルールを“親が一方的に決めない”こと。子どもと一緒に話し合いながら決めることで、「自分で守る意識」が芽生えます。小さな約束を守ることで、責任感や自己管理能力も育つんですよ。
家庭ごとにルールの内容は違ってOK。大事なのは、「使い方に一貫性を持たせること」なんです。
最初の設定次第で、家庭内の“デジタルの空気”が変わります。ここが一番のポイントです。
②おすすめの学習アプリと活用法
タブレットを学習に活かすなら、「どんなアプリを使うか」がカギになります。平愛梨さんの家庭では、年齢や興味に合わせて複数のアプリを使い分けているそうです。
| ジャンル | おすすめアプリ | 特徴 |
|---|---|---|
| 知育・基礎学習 | 「シンクシンク」 | 思考力を鍛えるゲーム形式の問題集。短時間でも集中力アップ。 |
| 英語学習 | 「Duolingo」 | ゲーム感覚で英語の文法や発音を学べる。 |
| プログラミング | 「ScratchJr」 | 幼児からでも使えるプログラミング入門アプリ。 |
| 創造系 | 「ibisPaint」 | 自由に絵が描けるデジタルアートアプリ。創造力を伸ばすのに最適。 |
このように、「学び系」「創作系」「表現系」をバランスよく取り入れるのがコツ。1日10分でも、継続すれば確実に力になります。
また、アプリを選ぶときは“子どもの好き”を最優先に。親が「良さそう」と思っても、本人が楽しめなければ続きません。まずは一緒に試して、笑顔で終われるアプリを選びましょう。
平愛梨さんも「子どもが夢中になっている姿が何よりの学び」と語っています。まさにその通りですね。
③使いすぎを防ぐ親の見守り方
タブレット教育を取り入れるうえで欠かせないのが、「使いすぎ対策」です。ここは多くの家庭が苦労するポイントですが、工夫次第でストレスなくコントロールできます。
おすすめなのが、タブレットに「スクリーンタイム」や「デジタルウェルビーイング」機能を設定すること。これで使用時間を自動的に制限でき、親子の衝突を減らせます。
また、親が“監視する”のではなく、“一緒に見守る”姿勢が大切です。「今日はどんなことを学んだの?」と声をかけるだけでも、子どもは「見られてる=褒めてもらえる」と感じ、意欲的になります。
視力や姿勢のケアも忘れずに。30分ごとに休憩を入れたり、ブルーライトカットメガネを使ったりするだけで健康面の不安も減らせます。
タブレットを「管理」ではなく「共有」する感覚で使うと、親も子もストレスフリーに続けられますよ。
④「紙」と「デジタル」をうまく両立させるコツ
タブレット学習ばかりに偏ると、「手で書く力」が衰えるという懸念もあります。平愛梨さんの家庭では、ここをとても大切にしていて、「タブレットは情報を得るもの、ノートは考えを整理するもの」と使い分けているそうです。
たとえば、タブレットで見た動画やクイズを、ノートに書いてまとめる。デジタルと紙の“往復学習”ができると、記憶の定着率がぐんと上がります。
これは教育学的にも有効で、実際に東京大学の研究でも「手で書くことが理解力を高める」と報告されています。つまり、紙を完全に捨てるのではなく、役割を明確にするのがポイントなんです。
家庭で実践するなら、「朝は紙」「夜はタブレット」など時間帯で分けてもいいですね。そうすると自然にバランスが取れます。
デジタルも紙も、それぞれの良さを活かしていく。これが平愛梨流の“ハイブリッド教育”です。
専門家が見る!子どもにタブレットを持たせる最適なタイミング
専門家が見る!子どもにタブレットを持たせる最適なタイミングについて解説します。
「子どもにいつからタブレットを持たせるべき?」——この質問は、親なら誰しも一度は考えますよね。ここでは、教育専門家や心理学者の見解を踏まえながら解説します。
①何歳から始めるのが理想?
結論から言うと、タブレットを「持たせる」時期は、5〜6歳ごろが理想だといわれています。これは、文部科学省が推進しているGIGAスクール構想でも、小学校入学時に1人1台の端末を支給していることからもわかります。
ただし、それより前の年齢でも、「一緒に使う」ことはおすすめです。たとえば3〜4歳のうちは、親と一緒に知育アプリを楽しむことで、操作に慣れたり、興味の幅を広げたりすることができます。
重要なのは、「渡す年齢」よりも「どう使うか」です。早く与えるのではなく、段階的に慣らしていくイメージが大切なんですよね。
平愛梨さんの家庭でも、幼児期からタブレットに触れさせていますが、必ず親の目の届く範囲で使わせています。この“共に使う”スタイルが理想形だといえます。
つまり、年齢に関係なく「親子で学びながら使う」ことこそが、ベストなタイミングなんです。
②発達段階に応じた使い方
タブレットの使い方は、子どもの発達段階によって変える必要があります。専門家たちは、以下のような使い分けを推奨しています。
| 年齢 | 使い方のポイント |
|---|---|
| 3〜5歳 | 親と一緒に知育アプリを使う。遊びながら操作を学ぶ。 |
| 6〜8歳 | 学習アプリを導入。学ぶ楽しさを体験させる。 |
| 9〜12歳 | 調べ学習や表現活動に活用。自立的な学びを促す。 |
| 13歳以降 | 目的を持って使わせる。情報リテラシー教育を重視。 |
こうして段階的に使い方を変えることで、子どもが混乱せず、自然に“学習ツール”としてタブレットを活用できるようになります。
ポイントは、「年齢が上がるほど自由度を増やす」こと。最初から完全に自由にすると、どうしても娯楽的な使い方に偏ってしまいます。
親が伴走しながら、少しずつ“手を離していく”——これが理想的なステップアップです。
③教育心理学から見た効果
教育心理学の観点からも、タブレットを活用した学びには多くのメリットがあることが明らかになっています。特に注目されているのが、「内発的動機づけ(自分から学びたいと思う力)」の向上です。
人は「自分で選んだ学び」ほど集中しやすく、記憶に残りやすいといわれています。タブレットは、その“選ぶ自由”を与えるツールなんです。
また、インタラクティブな教材は脳の「報酬系」を刺激しやすく、楽しく学べるため、継続力が高まる傾向もあります。ゲーム的な仕組みが学びのモチベーションを支えてくれるんですよね。
ただし、心理学者の多くは「報酬(ポイントやバッジ)だけを目的にしないこと」が重要だと指摘しています。褒められるよりも、「学んで面白かった」と感じさせることが大事なんです。
そのためにも、親が「どんなことを学んだの?」と聞いてあげることで、学びが“承認”され、自己効力感が育ちます。これが継続学習の鍵になります。
④家庭でできるデジタル教育の工夫
最後に、家庭で今日から実践できる“デジタル教育のコツ”を紹介します。どれも簡単ですが、効果は抜群です。
- リビング学習を基本にして、親の目が届く環境を作る。
- 使用時間を「タイマー」で管理し、約束を可視化する。
- 使う前に「今日は何を学ぶの?」と目的を確認する。
- 1日の終わりに「どんなことができた?」と振り返る。
これらを意識するだけで、タブレットは“遊び道具”から“学びの相棒”に変わります。特に「振り返り」を習慣化すると、子どもの成長スピードがグンと上がります。
平愛梨さんのように、親が“共に学ぶ姿勢”を見せることが、何よりも大切なんですよね。親の背中が、子どもの最初の教科書なんです。
タブレット教育は、家庭の環境づくり次第で、最高の学びの道具になります。
まとめ|4児の母・平愛梨に学ぶ、これからの時代の「家庭教育」
| まとめトピック |
|---|
| 平愛梨が語る教育への思い |
| なぜ「1人1台」なのか?その背景 |
| 家庭でのルールと使い方 |
| 長友佑都との教育観の違い |
| タブレット導入で変わった子どもの様子 |
4児の母として奮闘しながらも、時代に合わせた教育を柔軟に取り入れている平愛梨さん。彼女の「子どもに1人1台タブレット」という選択は、単なる話題づくりではなく、深い教育哲学に基づいたものでした。
一番のポイントは、「タブレットを与えること」ではなく「どう使うか」。親が管理者ではなく、伴走者として子どもの学びを支える姿勢が印象的でしたよね。
デジタル化が進むこれからの時代、タブレットは“避けるべきもの”ではなく、“一緒に育てていくツール”です。平愛梨さんの家庭のように、ルールと信頼を両立すれば、タブレットは子どもの世界を広げる最強の味方になります。
また、夫・長友佑都さんとの教育観のバランスも素敵でした。「デジタル」と「リアル」、「学び」と「体験」を両立させることで、子どもたちが多面的に成長できる環境を作り上げています。
そして何より、親が楽しそうに学びに関わっている姿は、子どもにとって最高の教育です。親が笑顔で学び、挑戦する姿勢を見せることで、子どもは自然と「学ぶって楽しい」と感じるようになります。
これからの家庭教育は、“デジタル×愛情”の時代。
タブレットをきっかけに、親子の絆をもっと深めていける未来が待っています。
もしあなたも「うちの子にもタブレットを持たせてみようかな」と感じたら、まずは一緒に触ってみてください。大切なのは、最初の「共に学ぶ一歩」です。
参考リンク:

、女優・高宗歩未(32-120x68.png)