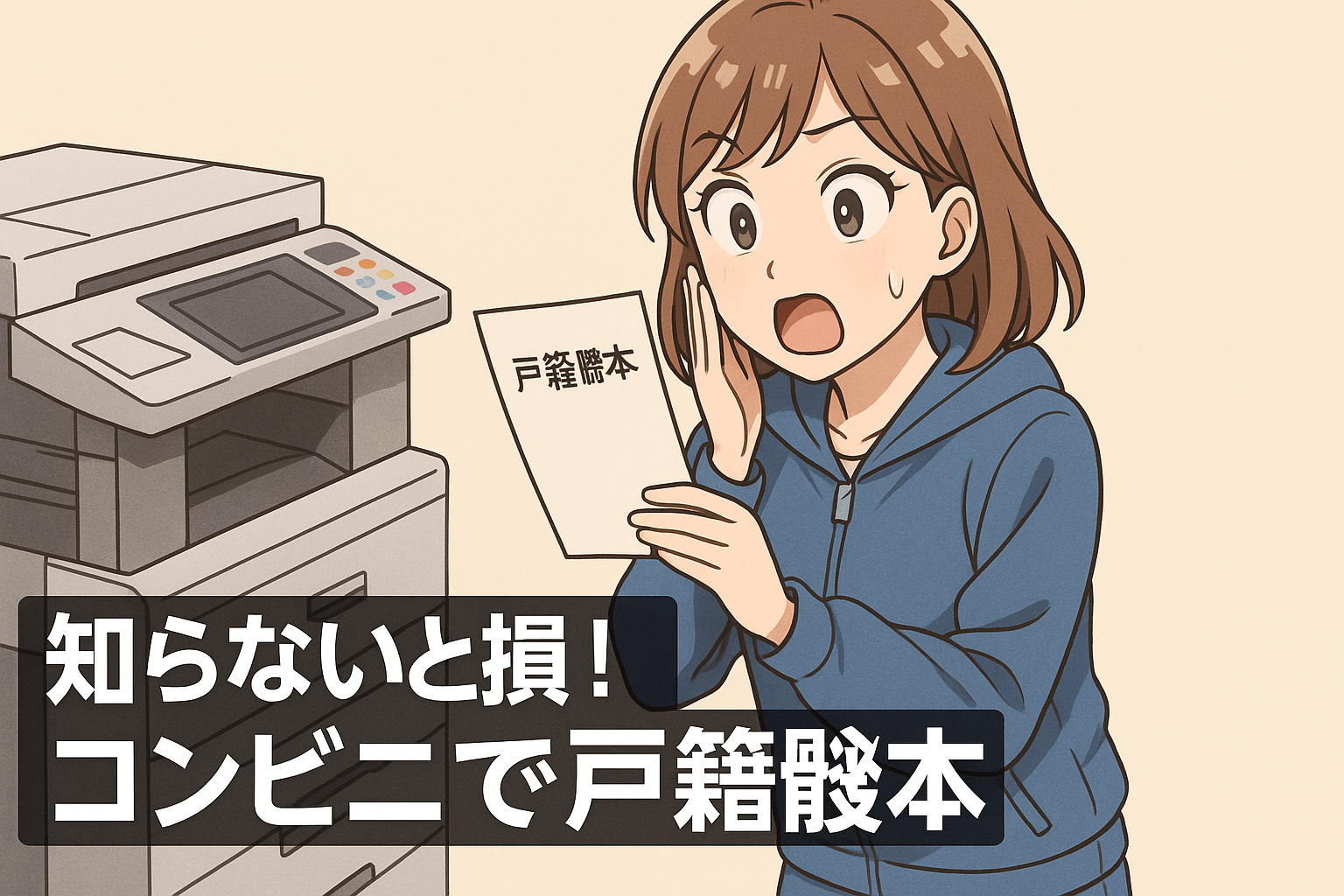「戸籍謄本が急に必要になったけど、平日は役所に行けない…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?
この記事では、コンビニで戸籍謄本を取得する方法をわかりやすく解説します。
マイナンバーカードが必要な理由や、本籍地が異なる場合の申請手順、注意点、さらにメリットとデメリットまで、完全網羅。
初めての方でも安心して利用できるよう、ステップごとに丁寧にご紹介しています。
この記事を読めば、今後「戸籍謄本、どう取るの?」と迷うことはありません。
ぜひ最後までチェックして、あなたの証明書取得ライフをラクにしていきましょう!
コンビニで戸籍謄本を取得する方法をわかりやすく解説
コンビニで戸籍謄本を取得する方法をわかりやすく解説します。
それでは順番に見ていきましょう。
①コンビニで取得できる戸籍証明書の種類
コンビニで取得できる戸籍関連の証明書は、主に「戸籍謄本(全部事項証明書)」と「戸籍抄本(個人事項証明書)」の2種類があります。
戸籍謄本は、同一戸籍に記載されている全員分の情報が載っているもので、家族全員の情報が必要な場面で使います。
一方で、戸籍抄本は本人または特定の人だけの情報を取得したいときに使う書類です。
また、自治体によっては「戸籍の附票」も取得できる場合があります。これは住所の履歴を証明するもので、転居歴などが必要な手続きに役立ちます。
ただし、すべての市区町村で全ての証明書に対応しているわけではないため、事前に確認しておくことが重要ですよ。
②マイナンバーカードが必須な理由
コンビニで戸籍謄本を取得するには、マイナンバーカードが必須です。
なぜかというと、キオスク端末(マルチコピー機)で本人確認を行うために、マイナンバーカードのICチップを読み取って利用者情報を認証する仕組みだからです。
また、カードには4桁の暗証番号が設定されていて、これを入力することでセキュリティを確保しています。
通知カードや住民基本台帳カードでは利用できないため、「顔写真付きのマイナンバーカード」を用意する必要があります。
暗証番号を忘れてしまった場合は役所で再設定が必要になるので、前もって確認しておくとスムーズに利用できますよ。
③対応している市区町村の調べ方
「コンビニで戸籍謄本が取れるのは本当に自分の市区町村でも可能なの?」という疑問を持つ人、多いと思います。
実際に使えるかどうかは、全国の市区町村ごとに異なります。
確認方法は簡単で、「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」の公式サイトで、自分の本籍地の市区町村を検索するだけ。
検索結果に「○」が表示されていれば、その自治体はコンビニ交付に対応していることを意味します。
もし「×」や「-」が表示されている場合は、対応していないため、コンビニでは取得できません。役所の窓口を利用しましょう。
④取得できる時間と曜日
コンビニ交付の最大のメリットの一つが、365日いつでも利用できることです。
原則として、6:30~23:00の間で証明書の発行が可能です(一部店舗・自治体を除く)。
市役所が閉まっている夜間や土日・祝日でも、コンビニでサクッと取得できるのはほんと便利ですよね。
ただし、システムメンテナンスの時間帯などは利用できない場合があるので、深夜や早朝に行く前には公式サイトなどでチェックしておくと安心です。
また、キオスク端末が設置されていない店舗もあるので、事前に設置店舗も調べておくといいですよ。
⑤料金と支払い方法
コンビニで戸籍謄本を取得する場合、手数料は基本的に役所での発行と同じか、少し安く設定されている自治体もあります。
多くの場合、1通450円程度が相場ですが、市区町村によって違いがあるため、公式サイトなどで確認してくださいね。
支払いは、キオスク端末での操作後にコインベンダーに現金を投入する形です。
一部店舗では電子マネーに対応していない場合もあるので、小銭を準備しておくと安心です。
レシートも発行されるので、会社などに提出する場合も安心ですよ。
本籍地が違う場合のコンビニ交付の手順とは
本籍地が違う場合のコンビニ交付の手順とはどういうものかを解説します。
それでは、具体的な手順をひとつずつ見ていきましょう。
①本籍地が遠方でも大丈夫?
結論からいうと、「本籍地が今の住まいと違っていても、条件さえ合えば大丈夫」です。
住民票がある市区町村と、本籍地が別の場所にあるという方は多いと思います。
この場合でも、事前に「本籍地の市区町村」で『利用登録』をすれば、コンビニで戸籍謄本が発行できるようになります。
この登録作業が済んでいないと、キオスク端末でエラーが出てしまうので注意が必要です。
本籍地が遠くて役所に行けない…という人でも、ネットや端末で登録ができるので安心してくださいね。
②利用登録申請が必要な理由
なぜこの「利用登録」が必要なのかというと、戸籍情報は非常に機密性の高い個人情報だからです。
自治体は、勝手に他の市区町村にある戸籍を誰でも引き出せるようにはしていません。
そのため「この人は本当にこの本籍地の人です」という確認作業が必要になります。
マイナンバーカードと本人確認の情報を紐づけて、本籍地側の自治体が許可を出す形ですね。
一度登録してしまえば、以降は毎回申請しなくてもスムーズに取得できますよ。
③キオスク端末からの申請手順
セブンイレブンやローソン、ファミマにある「マルチコピー機」などのキオスク端末から申請する方法を説明します。
まず、端末の「行政サービス」→「証明書交付」→「戸籍証明書交付利用登録申請」を選びます。
その後、画面に沿って本籍地の都道府県・市区町村を選び、自分の本籍の番地や氏名、連絡先などを入力します。
このときマイナンバーカードの暗証番号も必要になりますので、忘れないようにしましょう。
申請が完了すると「申請番号」が表示されるので、これをメモか印刷しておくと後で状況確認ができます。
登録が完了するまでは、数日から最大1週間ほどかかる場合もあるので、余裕をもって行動してくださいね。
④インターネットからの申請方法
自宅にICカードリーダー付きのパソコンがある場合は、もっと便利にインターネット申請ができます。
「戸籍証明書交付の登録申請サイト」(J-LISの公式サイト)にアクセスし、画面の案内に従って手続きを進めます。
手順としては、ICカードリーダーにマイナンバーカードを読み取らせた後、利用者情報を入力して送信するだけ。
もちろん暗証番号も必要になりますし、カードの有効期限などもチェックされるので、事前に確認しておきましょう。
申請完了後に表示される「申請番号」で、ステータスを後から確認できます。
ネット環境が整っていれば、わざわざコンビニまで出向かなくても、登録作業が完了するのはありがたいですよね。
マイナンバーカードを使うときの注意点5つ
マイナンバーカードを使うときの注意点5つについて解説していきます。
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
①暗証番号を忘れると利用できない
マイナンバーカードで証明書を取得する際に最も重要なのが「暗証番号の入力」です。
この4桁の暗証番号は、ICチップに登録された情報へのアクセスに必要不可欠なんです。
もし暗証番号を忘れてしまった場合、その場で再設定はできず、役所に行って手続きをし直す必要があります。
しかも何回も間違えるとロックされてしまうので要注意です。
コンビニで証明書を取りたい当日に「暗証番号がわからない…」なんてことになると目も当てられませんので、前もって確認しておいてくださいね。
②有効期限切れに注意
マイナンバーカードには、有効期限がしっかり設定されています。
特に20歳未満の方は5年、有効期限が比較的短めなんですよね。
有効期限が切れているカードは、コンビニ交付など一切のサービスに使えなくなります。
カードの表面に記載されている有効期限を確認し、切れていたら市役所で更新手続きをしてください。
「いざ必要なときに使えなかった…」なんてことにならないように、期限チェックはお忘れなく!
③セキュリティコードの確認
セキュリティコードって、意外と見落としがちなんですけど、これもとっても重要です。
このコードは、暗証番号とは別でマイナンバーカードに記載されている番号です。
端末によってはこの番号の入力を求められることがあります。
つまり、マイナンバーカードを持っていても、セキュリティコードが不明だとその場で詰むんです。
カードを発行したときにもらった封筒や、控えの資料などで事前にチェックしておくと安心ですね。
④カードリーダーの反応が悪いとき
コンビニのキオスク端末でカードを読み取る際、「あれ?反応しない…」なんて経験ありませんか?
カードのICチップ部分が汚れていたり、挿入の向きが間違っていたりすると、うまく読み取れないことがあります。
また、寒暖差でカードが結露してしまうと読み取りに支障が出ることも。
そういうときは、端末の画面をよく確認して、カードの置き方を調整してみましょう。
それでもダメなら、店員さんに聞くのではなく、近隣の別の店舗を使う方が早かったりしますよ。
⑤他人のカードでは取得不可
当たり前のことですが、他人のマイナンバーカードを使って戸籍謄本を取得することはできません。
コンビニ交付は「本人確認」がベースにある仕組みなので、カード所有者本人でないと全く操作できないんです。
「家族の証明書を代わりに取りたい」というケースでも、原則NGです。
どうしても代理で必要な場合は、役所で委任状を提出するなどの別手続きが必要になります。
家族でも使い回しができない点はしっかり理解しておきましょうね。
戸籍謄本を急ぎで必要なときの対処法
戸籍謄本を急ぎで必要なときの対処法について詳しく解説します。
戸籍謄本が「今すぐ必要!」というときのために、できる対処法を確認しておきましょう。
①コンビニ非対応の市区町村だった場合
戸籍謄本をコンビニで取得できるのは便利ですが、実はまだ全ての市区町村が対応しているわけではありません。
コンビニ交付が使えない自治体の場合、代替手段としては役所に直接行くか、郵送請求の2択になります。
ただ、平日の昼間に役所へ行くのが難しいという方も多いと思います。
その場合は、まず「本籍地の役所のサイト」で郵送請求のやり方をチェックしましょう。
申請書のダウンロード、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替などが必要になりますが、早ければ数日で届きますよ。
②早朝・深夜に取得するには
「明日の朝一に提出しなきゃいけないのに、今から準備して間に合う?」
そんなときに活躍するのが、やっぱりコンビニ交付サービス。
多くの自治体では朝6:30から夜23:00まで利用可能なので、深夜に必要になっても対応できます。
ただし、マイナンバーカードや事前の利用登録が済んでいることが前提なので、緊急の時ほど事前準備の有無が重要になります。
「いざというときのために、カードの準備と登録だけは先に済ませておく」これ、めちゃくちゃ大事です。
③必要部数の追加があるとき
戸籍謄本を取得したあと、「あれ?もっと必要だったかも!」というケース、けっこうあるあるです。
コンビニのキオスク端末では、1回の手続きで複数部数の取得が可能です。
発行前の最終確認画面で、必要部数を入力すればOK。
でも一度発行してしまった後で「もう1通必要!」となったら、もう一度最初から操作しなおす必要があります。
料金もその都度かかるので、最初から必要枚数をよく確認しておくのがベストですね。
④他の取得方法(郵送・役所)
コンビニが使えない、カードを忘れた、暗証番号がロックされた…そんなときはどうすればいいか?
一番確実なのは、やはり「本籍地の役所」に直接出向くことです。
ただ、遠方に住んでいる人にとっては現実的じゃないですよね。
その場合、郵送請求が非常に有効です。各自治体の公式HPから申請用紙をダウンロードし、記入して送付します。
添付するのは「本人確認書類のコピー」「手数料分の定額小為替」「返信用封筒(切手付き)」など。
ちょっと手間はかかりますが、確実に入手できる方法なので、最終手段として覚えておいて損はないですよ。
コンビニで戸籍謄本を取得するメリット・デメリット
コンビニで戸籍謄本を取得するメリット・デメリットについて詳しく解説します。
それぞれの利点と不便な点を、正直に見ていきましょう。
①役所に行かなくていい手軽さ【メリット】
一番の魅力はなんといっても「役所に行かなくてもいい」ってこと。
平日仕事で忙しくて市役所の開いてる時間に行けない人にとって、これはありがたいですよね。
近所のセブンイレブンやローソン、ファミマに立ち寄るだけで戸籍謄本が手に入るなんて、数年前までは考えられなかった便利さです。
待ち時間ゼロ、人混みゼロ、書類記入も最小限。
本当に「ちょっと買い物ついでに証明書も取って帰ろう」くらいの感覚で利用できるのは大きなメリットです。
②土日祝日も利用できる【メリット】
市役所は基本的に土日祝日は休みですが、コンビニ交付ならその心配はありません。
利用可能時間内(例:6:30~23:00)なら、曜日問わずいつでも使えるのがうれしいポイントです。
急に必要になったときでも、平日を待たずに対処できるのは助かりますよね。
とくに、提出期限ギリギリで焦っているときはこの「いつでも取れる」安心感が心強いです。
日曜の夜に「あ、戸籍謄本必要だった!」となっても、なんとかなっちゃうのが本当にありがたいですね。
③即時発行で時間短縮【メリット】
もうひとつの大きな魅力が「即時発行」です。
端末で操作して、支払いを済ませれば、数分でその場でプリントアウトされるというスピード感。
役所で並んで番号札を取って、窓口で順番待ちして、なんてことを考えると、その差は歴然ですよね。
移動時間も手続き時間もまるっとカットできるので、時間を大切にしたい人にはピッタリです。
スピード勝負のビジネスパーソンや、育児中のママさんパパさんにも大助かりだと思います!
④マイナンバーカードが必須【デメリット】
ただし、すべての人が使えるわけではないのがこの制度の難点。
利用には「顔写真付きのマイナンバーカード」が必須条件になります。
通知カードやマイナンバーだけを知っている状態では利用できません。
また、カードがあっても暗証番号を忘れていたり、ロックされていたりすると使えないんですよね。
便利な反面、条件が少しシビアなので、事前の準備や管理が必要です。
⑤全ての市区町村が対応していない【デメリット】
もう一つの注意点は、コンビニ交付が「全国一律で使えるわけではない」ということ。
対応している市区町村と、そうでない市区町村がまだ混在しているのが現状です。
特に地方自治体では、導入されていないケースも少なくありません。
自分の本籍地が対応しているかどうかは、J-LISの「コンビニ交付 対応自治体検索」で事前にチェックする必要があります。
「コンビニ行ったのに使えなかった…」なんてことが起きないように、確認はしっかりしておきましょう。
まとめ|コンビニで戸籍謄本を取得する方法を知っておくと安心
| 取得に関するポイント |
|---|
| ①コンビニで取得できる戸籍証明書の種類 |
| ②マイナンバーカードが必須な理由 |
| ③対応している市区町村の調べ方 |
| ④取得できる時間と曜日 |
| ⑤料金と支払い方法 |
コンビニで戸籍謄本を取得する方法は、手軽で便利ですが、いくつかの条件と準備が必要です。
特にマイナンバーカードの取得と事前の利用登録がカギになります。
この記事でご紹介したように、対応自治体を確認して、暗証番号や有効期限の確認をしておけば、いざというときも慌てずに済みます。
本籍地が遠方の方や、仕事で平日に時間が取れない方にとって、コンビニ交付はまさに強い味方です。
これからマイナンバーカードを取得する方も、すでに持っている方も、ぜひ一度試してみてください。
詳しい対応自治体や登録申請はこちらから確認できます: