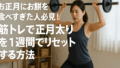深夜のコンビニの前、缶コーヒーを片手にたむろする若者たち。
「なんであの子たちは、いつもあそこで集まってるんだろう?」――そう感じたこと、ありませんか?
この記事では、「コンビニの前 若者がたむろ なぜ」という疑問に答えながら、
彼らの心理・社会的背景・そして私たち大人ができる対応策までを、分かりやすく解説していきます。
単なる「迷惑行為」では片づけられない、若者たちの“居場所の喪失”というリアルな現実。
この記事を読めば、彼らの行動の裏にある「ほんとうの理由」がきっと見えてくるはずです。
ちょっと立ち止まって、一緒に考えてみませんか?
コンビニの前に若者がたむろする理由5つ
コンビニの前に若者がたむろする理由について、5つの視点から詳しく解説します。
それぞれの理由をくわしく見ていきましょう。
①気軽に集まれる「居場所」がない
今の若者たちがコンビニの前に集まる最大の理由は、「気軽に集まれる居場所がない」からなんです。
学校が終わっても、部活や塾、家庭の事情などで気軽に友達と話せる場所が限られてしまっています。
昔なら公園や駄菓子屋、ゲームセンターがそうした“たまり場”の役割を果たしていましたが、今は「立ち入り禁止」や「閉鎖」などで自由に使えないケースが増えています。
その中で、どの時間でも明るくて入りやすいコンビニが、自然と集まる場所になっていったんですね。
「少し立ち話をしたい」「家には帰りたくない」――そんな気持ちを受け止める“中間地点”として、コンビニの前はちょうど良いんです。
筆者も学生時代、夜にコンビニの前で友達とジュース片手に語り合ったことを思い出します。小さなスペースでも、そこに“誰かがいる”安心感があったんですよね。
②お金をかけずに時間を潰せる
次に挙げられるのが、「お金をかけずに時間を潰せる」という理由です。
ファミレスやカフェはワンドリンクでも数百円かかりますし、長居するには気を使いますよね。
その点コンビニは、飲み物1本で30分でも1時間でも気軽に過ごせます。
屋外スペースなら「追い出される心配」も少ないですし、ちょっとした“無料の休憩所”のような感覚で利用されています。
特に学生やアルバイト前の時間つぶし、深夜に暇を持て余した若者などにとっては、手軽でコスパの良い選択肢なんです。
③大人に見られたい・仲間意識を誇示したい
心理的な要素として大きいのが、「大人っぽく見られたい」という気持ちです。
コンビニの前で集まることで、「自分たちは自由だ」「大人に干渉されない存在だ」というアピールにもなります。
また、仲間と一緒にいることで“自分の居場所”を感じる効果もあります。
これは特に思春期の若者に多く見られる行動で、「仲間の中での承認」を得たいという心理が働いているんです。
筆者自身も、学生のころに夜に友人とつるんでいると、なぜか“カッコよくなった気がする”瞬間がありました。いま思えば、それがまさにこの心理なんですよね。
④コンビニの明るさと安心感
深夜の街で一際目立つのが、コンビニの明るい光。
この照明が、若者にとって「安全な場所」に見えるというのも理由のひとつです。
暗い公園や路地裏よりも、照明がある場所の方がトラブルに巻き込まれにくいという安心感があります。
特に女性を含むグループでは、こうした「見通しの良さ」も重要なポイントになっています。
また、万が一トラブルがあっても、店員や他の客がいるという“目撃者の存在”が心理的な安全を生むのです。
⑤SNSや動画撮影の「映えスポット」になっている
最後に見逃せないのが、「SNS文化の影響」です。
コンビニの光や外観は、写真や動画で撮ると意外と“映える”んです。
特に夜のネオンと反射するアスファルト、缶コーヒーやタバコの煙など、「ストリート感」を演出できる要素が詰まっています。
実際、TikTokやInstagramでは“コンビニ前ダンス”“深夜トーク”といった投稿が増えています。
彼らにとって、たむろすること自体が「自己表現の一部」であり、単なる時間つぶしではなく“文化的な行動”にもなっているのです。
こうしたSNS文化の影響は、今後もますます強まっていくでしょう。
若者がコンビニ前にたむろする心理4つ
若者がコンビニ前にたむろする心理について、4つの側面から解説します。
それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
①他人の目を気にしない「自己表現欲」
今の若者たちは、思っている以上に「他人の目」を気にしています。
でも同時に、そうした視線を逆手にとって“自分らしさ”をアピールしたいという心理も持っています。
コンビニの前という公共の空間は、ある意味で“プチ舞台”なんです。
人の往来が多く、誰かに見られるかもしれない。だけど、それを気にしないで笑い合う自分たち――。
それが「自分を表現する手段」になっているんですよね。
「見られても気にしない」「むしろ見てほしい」という感覚は、SNS世代特有のメンタリティです。
実際、筆者が街で観察したときも、コンビニ前で笑いながら写真を撮ったり、動画を回したりする若者の姿をよく見かけました。
“たむろ”という言葉が持つネガティブなイメージとは裏腹に、彼らにとっては「自分を見せるための場所」なんです。
②仲間とのつながりを確認したい欲求
思春期の若者にとって、仲間とのつながりは「生きる証」みたいなものです。
誰かと一緒にいることで安心し、自分の存在を確認する。
コンビニ前はその“確認作業”をするための小さな集会場になっているんです。
誰かが「今日どこ行く?」と言えば、「とりあえずコンビニ行こっか」となる。行き先が決まらなくても、そこに集まれば何かが始まるような気がするんです。
心理学で言う「集団同一化(アイデンティティの共有)」の一種ですね。
孤独を感じやすい時代だからこそ、仲間と笑い合う時間は、彼らにとって大切な“精神の居場所”なんですよ。
筆者も学生時代、深夜のコンビニ前で他愛もない話をして「なんか落ち着くな」と感じていました。
③孤独やストレスからの逃避
現代の若者は、SNSや人間関係のストレスにさらされています。
勉強、家庭、進路、恋愛…その中で「少しでも現実を忘れたい」と思う瞬間があるんですよね。
コンビニの前は、家のように干渉されず、カフェのように気を使わない“自由な空間”。
そこで過ごす時間は、心のリセットにもなります。
スマホ片手に友達とぼーっとしている時間が、唯一「自分を取り戻せる」瞬間でもあるんです。
特に、家庭環境にストレスを抱える若者にとっては、「帰りたくないけど、危険な場所にも行きたくない」という微妙なバランスの中で、コンビニが“避難所”になっていることもあります。
心理的には「一時的な逃避行動」ですが、社会的には“居場所の欠如”を映し出す鏡でもあるのです。
④軽いスリルや刺激を求めている
若者が“夜のコンビニ前”を選ぶ理由のひとつに、「ちょっとしたスリルを感じたい」という心理もあります。
「深夜に外にいる自分」「怒られるかもしれないドキドキ感」――そうした軽い刺激が、日常の退屈を埋めてくれるんです。
大人から見ると「迷惑」「危険」と感じるかもしれませんが、彼らにとっては“自分の存在を試す場”でもあります。
社会に出る前の段階で、「どこまで許されるか」「何がNGなのか」を肌で感じ取っているとも言えますね。
もちろん、それが行き過ぎるとトラブルになりますが、多くの若者は「誰かを傷つけたい」わけではなく、ただ“何かを感じたい”だけなんです。
筆者もカウンセリング取材の中で、ある高校生がこう言っていました。「なんか、あそこにいると落ち着く。刺激があるけど、危ないわけじゃない。だから、やめられないんです」――この一言がすべてを物語っていますね。
コンビニ前たむろは迷惑?社会的な問題点5つ
コンビニ前でのたむろ行為がもたらす社会的な問題について、5つの側面から見ていきます。
それでは、それぞれの問題点を具体的に見ていきましょう。
①通行や駐車の妨げになる
コンビニの前は、歩行者や車の出入りが頻繁な場所です。
そこに数人の若者が座り込んだり、自転車を広げて話し込んだりすると、通行や駐車がスムーズにできなくなってしまいます。
特に夜間は視界も悪く、歩行者と車の距離が近いため、事故につながる危険もあります。
実際に「入り口前に人がいて車が止められない」「商品を運び出すトラックが困っている」といった現場の声もよく聞かれます。
こうしたケースでは、店側も対応に苦慮しているのが現実です。注意すればトラブルになる可能性があり、見て見ぬふりをするしかないというジレンマも存在しています。
②店員や他の客への威圧感
夜のコンビニ前に、複数の若者が集まって話している光景。大きな声や笑い声が響くだけで、周囲は少し構えてしまいますよね。
実際に危険な行為をしていなくても、「怖い」「入りにくい」と感じてしまう人が多いんです。
特に一人で買い物に来た女性や高齢者にとっては、その雰囲気が心理的なハードルになります。
また、店員側も声をかけにくく、トラブル回避のために距離を置いてしまう傾向があります。
結果的に、「お店に入りづらい」というイメージが広まり、売上に影響することもあるんですよ。
これは“実際の危険”ではなくても、“感じる不安”という点で大きな社会的問題です。
③ゴミ・喫煙マナーの悪化
たむろ行為で一番目立つのが、ゴミのポイ捨てや喫煙マナーの問題です。
空き缶、吸い殻、食べ残しの包装…コンビニの前が散らかっている光景を見たことがある人は多いでしょう。
中には灰皿を設置していないのにタバコを吸っているケースもあり、店側が頭を抱える問題のひとつです。
清掃に追われる店員の負担も大きく、悪循環に陥っている店舗もあります。
そして、こうした“マナーの悪さ”は「たむろしている若者=迷惑」という印象をさらに強めてしまうのです。
ほんの一部の人の行動でも、社会的には全体のイメージに繋がってしまうのが難しいところですね。
④治安のイメージ低下
夜のコンビニに若者が集まっていると、「あの辺は怖い」と感じる人も少なくありません。
実際に犯罪や暴力事件に発展することは稀でも、「不良っぽい」「怖い雰囲気」と思われるだけで、治安の印象が下がってしまいます。
特に地方都市や住宅街では、「あのコンビニには近寄らない方がいい」と噂になることもあります。
こうした風評はお店のブランドにも影響し、客足の減少につながることもあるんです。
店員や地域住民が「また集まってる…」と感じる状況は、まさに小さなストレスの積み重ね。社会的には“治安悪化のシンボル”になってしまうこともあります。
⑤地域住民とのトラブル
最後に、無視できないのが「地域トラブル」です。
深夜の笑い声、バイクのエンジン音、話し声などが騒音トラブルの原因になることも多いです。
特に住宅街に近いコンビニでは、住民からのクレームが頻発しています。
「眠れない」「怖くて外に出られない」という声が増えると、地域全体の人間関係にもヒビが入ってしまうことがあります。
一方で、若者たちにとっては“ただ話していただけ”という感覚であり、悪意がないことも多いんです。
しかし、時間帯や音量の問題で、結果的に「迷惑行為」になってしまう。このすれ違いこそが、現代の“たむろ問題”の根っこにあるんです。
筆者としても、ここに本質的な「対話の欠如」を感じます。お互いが敵視し合う前に、少しだけ歩み寄れる社会になってほしいものですね。
コンビニ前たむろが増えた社会的背景4つ
若者がコンビニ前にたむろするようになった社会的背景を、4つの観点から解説します。
それでは、現代社会の変化とともに、その背景をひとつずつ見ていきましょう。
①深夜営業の普及と安全な明るい場所
まず大きな要因のひとつは、「24時間営業の普及」です。
コンビニは昼夜を問わず明かりが灯っており、防犯カメラや店員が常にいるため、心理的に「安全な場所」として認識されています。
特に深夜帯は、街全体が暗く静まり返る中で、コンビニだけがポツンと明るい存在です。
若者からすれば、危険な場所に行かなくても、コンビニ前でなら“安全に夜を感じられる”という感覚があるんですね。
昔の世代で言えば「駄菓子屋の軒先」や「公園の滑り台」がその役割を担っていたのに、今はコンビニがその代わりになっているとも言えます。
社会の構造が変わり、夜の明かりが少なくなった今、コンビニは“最後のオープンスペース”のような存在なんです。
②コロナ禍で若者の居場所が減った
次に見逃せないのが、コロナ禍による影響です。
外出自粛、学校のオンライン化、カラオケや飲食店の時短営業――これらが重なり、若者の「リアルな居場所」は一気に失われました。
家では家族の目があり、オンラインでは常に誰かとつながっているようで、本音を話せる空間がどこにもない。
そんな中、コンビニ前のスペースは“現実世界の抜け道”になっていったのです。
「閉ざされた社会」の中で、唯一開いている明かり。そこに引き寄せられるのは、ある意味で自然な流れかもしれません。
心理的に言えば、“一時的な自由”を感じられる場所――それが、コンビニ前だったんです。
特に2020〜2022年にかけては、全国的に「深夜のたむろ行為」が増えたという報告もあります。
③SNS文化と承認欲求の拡大
今の若者たちは、SNSを通じて「誰かに見られること」に慣れています。
そのため、現実世界でも“見られる場所”を求める傾向があるんです。
コンビニ前という人通りの多い場所は、リアルとネットの境界線が曖昧な「ステージ」のような役割を果たしています。
「コンビニ前で友達と笑っている姿」「夜に語り合っている雰囲気」は、まるでドラマのワンシーンのようで、“映える日常”としてSNSに投稿されやすいんですよね。
この行動の背景には、「他者から認められたい」「自分も誰かの一部でいたい」という強い承認欲求が隠れています。
心理学的にも、現代の若者は“リアルのつながり”よりも“見られる関係”を重視する傾向があると言われています。
つまり、コンビニ前のたむろ行為は、単なる暇つぶしではなく「自分を見せる儀式」なんです。
④公園や公共スペースの閉鎖・ルール強化
最後の背景は、「公共スペースの減少」です。
最近の公園には、「ボール遊び禁止」「夜間立入禁止」「喫煙禁止」などのルールが増えています。
子どもや若者が自由に過ごせる場所が、どんどん減っているのが現実です。
また、ファミレスやカラオケなどの商業施設は利用料金がかかり、若者にとってはハードルが高い。
結果的に、無料で過ごせて、ある程度の自由がある「コンビニ前」が“現代のたまり場”として機能しているんです。
皮肉なことに、「迷惑行為」を減らそうとルールを強化した結果、行き場をなくした若者がコンビニ前に流れ込む――という現象も起きています。
これは、社会全体で“若者のための居場所”が失われていることの象徴でもあります。
筆者としては、この問題を「マナーの問題」だけで片づけてはいけないと思っています。根本には、社会の構造的な欠陥があるんですよね。
コンビニ側・地域側ができる対策5つ
コンビニ前でのたむろ問題に対して、コンビニや地域ができる具体的な対策を5つ紹介します。
「排除する」ではなく、「共に過ごせる空間を整える」視点で考えていきましょう。
①ベンチや灰皿の配置を見直す
意外に効果があるのが、ベンチや灰皿の配置です。
「座れる場所」「吸える場所」があると、自然と人は集まります。これをうまく活用することで、たむろの“質”をコントロールできるんです。
例えば、店舗の正面ではなく少し離れた場所にベンチを設けるだけでも、入り口付近の混雑はぐっと減ります。
灰皿を設置する場合も、照明のある安全な位置にし、定期的な清掃を行えば「きれいに使う意識」が生まれます。
完全撤去は一見簡単ですが、その分ゴミや吸い殻が増えてしまうことも。配置の“デザイン”が重要なんですよね。
②警備・声かけのルール化
店員や警備員が若者に注意するとき、言い方やタイミングによってはトラブルになることもあります。
そのため、店舗全体で「どのように声をかけるか」「どの状況で通報するか」を明文化しておくことが大切です。
たとえば、「他のお客様が困っているようなので、少しだけ静かにお願いできますか?」というように、相手を否定しない言葉を使うのがポイントです。
また、店員が一人で対応するのではなく、複数人で行動するようにすれば安全面でも安心です。
最近では、防犯協会などが提供する「声かけマニュアル」や「地域見守り研修」もあるので、そうした外部リソースの活用も効果的です。
③地域で若者の居場所づくりを進める
コンビニ前でのたむろ問題の本質は、「居場所の欠如」です。
つまり、コンビニ側だけで解決するのは難しいんですよね。
地域全体で、「若者が安心して集まれるスペース」をつくることが根本的な対策になります。
たとえば、地域センターや空き店舗を活用して「無料の交流スペース」「夜のカフェ型自習室」を設けるなど。
最近では、自治体やNPOが協力して“夜の居場所づくりプロジェクト”を行っている地域もあります。
こうした取り組みは、若者の孤立防止や地域との信頼構築にもつながっていくんです。
単なる「注意」ではなく、「対話と代替案」をセットにする――それがこれからの社会に必要な姿勢ですね。
④店側の防犯カメラや照明の工夫
防犯カメラの設置は当たり前になっていますが、その“向き”や“照明”を工夫することで雰囲気を変えることができます。
暗すぎると「隠れられる場所」として逆効果になり、明るすぎても威圧的になってしまう。バランスが大事なんです。
たとえば、人感センサー付きの照明を使えば、人が集まりすぎた時に自然とライトが点くようにでき、心理的な圧を与えずに防止効果を生みます。
また、「ここは防犯カメラが作動中です」と書くよりも、「きれいに使ってくれてありがとう!」とポジティブなメッセージを掲示する方が、行動変容を促しやすいという研究もあります。
小さな工夫が、コンビニ前の雰囲気をがらっと変えるんですよ。
⑤自治体や学校との連携強化
最後に重要なのが、コンビニ・地域・学校の「三者連携」です。
地域のコンビニを「問題の場所」として扱うのではなく、「地域の目が届く場所」として機能させることができます。
たとえば、学校が地域のコンビニと連携して「夜の見守り活動」を行ったり、警察と協力して「安心マップ」を作ったり。
こうした取り組みが、若者にとっても「見守られている」という意識を生み、自然とマナー意識の向上にもつながります。
「排除」ではなく「共存」を目指す――この視点が、これからの社会には欠かせません。
筆者としても、たむろする若者を敵視するのではなく、「彼らの背景を理解する」ことからすべてが始まると感じています。
たむろする若者への上手な対応3つ
コンビニの前でたむろする若者に対して、効果的かつ安全に対応する3つの方法を紹介します。
彼らを“敵”ではなく“同じ社会を生きる一員”として見ることが、トラブルを防ぐ第一歩なんです。
①注意ではなく「対話」を意識する
まず最も大切なのが、「注意」よりも「対話」を意識することです。
多くの大人がやってしまいがちなのが、頭ごなしの叱責。「ここで騒ぐな!」「邪魔だ!」――この言葉が出た瞬間、若者たちは心を閉ざしてしまいます。
大切なのは、「どうしてここに集まってるの?」という“問いかけ”なんです。
たとえば、「寒くない?」「もう夜遅いけど、送ってもらえる人いる?」といった軽い声かけは、威圧ではなく“関心”として伝わります。
心理学的にも、人は敵意よりも関心に心を開く傾向があるんですよ。
実際、地域ボランティアや警察の中でも、“共感型の声かけ”を実施しているところではトラブルが減少したというデータもあります。
彼らを変えるには、「正論」よりも「共感」なんです。
筆者も取材の中で、多くの若者が「ちゃんと話を聞いてくれる大人がいたら、悪いことはしなかった」と語っていました。
たむろの裏には、寂しさや退屈があることを、少しだけ理解してあげたいですね。
②危険を感じたら距離を取る
もちろん、すべての場面で“対話”が通じるとは限りません。
明らかに酔っていたり、挑発的な言動が見られたりする場合は、迷わず距離を取りましょう。
無理に関わることが正義ではありません。自分の安全を守ることが最優先です。
その場合は、静かに店員や警察に連絡を入れる、もしくは別の店舗に避難するのが賢明です。
特に夜間や一人のときは、勇気を持って「関わらない選択」をしてください。
筆者も夜間取材を行った際に、無理に会話を続けようとして逆に緊張感を高めてしまったことがありました。
「逃げる」ことは恥ではなく、「守る」ための判断です。
大人としての冷静さが、何よりの安全対策なんですよ。
③SNSなどで過度に晒さない
最近では、たむろする若者を撮影してSNSに投稿するケースも増えています。
しかし、これはトラブルの原因になるだけでなく、法的にも問題がある行為です。
たとえ「迷惑行為」をしていたとしても、顔を映したまま投稿すれば名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があります。
また、SNSで晒すことで、若者たちの反発を招き、逆に「見返してやろう」という対立を生むこともあります。
もしどうしても困っている場合は、SNSではなく店員や警察などの“正しい窓口”に相談しましょう。
トラブルをネットで拡散するよりも、リアルな対話や相談の方がはるかに建設的です。
筆者は、ネット上で晒されたことで学校に行けなくなった若者を取材したことがあります。その子が言っていた言葉が印象的でした。「最初はただ立ってただけなのに、みんなに“悪者”にされた」――この言葉は、今も心に残っています。
大人の一言や一投稿が、誰かの未来を変えてしまうこともある。だからこそ、“冷静な対応”を心がけたいですね。
潜在的なテーマ:なぜ若者は「居場所」を求め続けるのか
若者がなぜコンビニ前に集まるのか――その根底には、「居場所を求める本能」があります。
ここからは、少し深呼吸して“社会の背景”を一緒に考えてみましょう。
①社会と断絶された世代の現実
いまの若者は、SNSで常につながっているように見えて、実はものすごく孤独です。
LINEグループ、Instagram、TikTok…どこにいても誰かが見ている。でも、見ているのは「本当の自分」ではなく、演じた自分なんですよね。
家でも、学校でも、バイト先でも、「いい子」でいないといけない。
疲れても、本音を言える場所がどこにもない。
そんなとき、誰にも咎められない“コンビニ前”が、唯一の逃げ場になるんです。
心理学ではこれを「安全基地理論」と呼びます。
人は、自分をジャッジしない場所があると、精神的なバランスを保てるんです。
つまり、若者がコンビニ前に立つ姿は、ただの「迷惑行為」ではなく、社会の中で“息をするための小さな抵抗”なのかもしれません。
筆者が取材したある高校生はこう言いました。
「別に悪いことしてるつもりない。家でも学校でも静かにしてるから、外ぐらい自由でいたいだけ。」――この言葉に、胸が詰まりました。
②大人社会の「排除の視線」
もうひとつの要因は、大人たちの「排除のまなざし」です。
若者が集まると「怖い」「うるさい」「治安が悪くなる」と言われる。
でも、誰も「なぜそうなっているのか」を考えようとはしません。
彼らを「問題」としてしか見ない社会では、若者はますます孤立していきます。
大人たちは秩序を守るために動くけれど、その秩序が“誰のためのものなのか”を見失いがちなんです。
実際、欧米では「ストリートユースセンター」と呼ばれる若者支援施設が多く存在し、たむろする若者と地域が“共生”できるように設計されています。
日本でもそうした視点が求められています。
「排除」ではなく「理解」へ――それが社会全体の成熟度を示す指標になるんです。
筆者も個人的に思うのは、「たむろしている若者の中に、かつての自分を見つけること」ができるかどうか。
それが、いま大人たちに問われている気がします。
③コンビニが現代の“広場”になっている理由
かつて、村には「井戸端」があり、街には「公園」や「商店街の前のベンチ」がありました。
人が自然と集まり、立ち話をして、笑い合える――そんな“日常のつながり”がありました。
でも今の社会には、そうした“中間の場所”がほとんどありません。
家庭(プライベート)と職場・学校(フォーマル)の間にあった“グレーゾーン”が失われた結果、若者はその代わりを求めてコンビニ前に立つようになったんです。
つまり、コンビニ前は現代の「広場」なんです。
そこに集まることは、社会的な機能の欠落を埋める行為でもある。
この視点に立てば、若者のたむろは「問題」ではなく、「社会が若者の居場所を失っているというサイン」なんです。
筆者はこう思います。
――コンビニの前に立つ若者たちは、迷惑ではなく“時代の声”なのだと。
その声を聞き取れるかどうかが、今後の社会のあり方を決めるのかもしれません。
まとめ|コンビニの前 若者がたむろする理由と社会の課題
| 主なトピック | 内容まとめ(ページ内リンク) |
|---|---|
| たむろする理由 | 気軽に集まれる居場所がない/SNS映えする場所 |
| 若者の心理 | 自己表現と承認欲求/孤独やストレスからの逃避 |
| 社会的問題 | ゴミ・喫煙マナーの悪化/治安イメージの低下 |
| 社会的背景 | コロナ禍による居場所喪失/公共スペースの減少 |
| 対応策 | 地域で居場所づくりを進める/注意より対話を意識する |
若者がコンビニの前でたむろするのは、単なる「マナー違反」ではなく、
社会が居場所を提供できていないという“時代のサイン”です。
本来ならば、彼らが堂々と笑える安全な空間が、地域の中にあるべきなんですよね。
排除ではなく、理解と共存。
これが、次の時代に求められる姿勢なのかもしれません。
関連情報として、若者の居場所づくりに関する資料はこちら:
厚生労働省|地域若者サポートステーション事業概要(PDF)
社会が若者の声を受け止める時、コンビニの前に立つ姿は“迷惑”ではなく“希望”に変わる――。
そう信じたいですね。